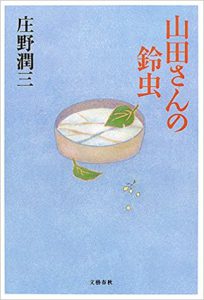二度と戻らない「今」の物語
多摩丘陵の山の上にある庄野邸を中心とする半径ほぼ百メートル圏内が、とりあえずこの物語の中心舞台です。庄野潤三と「妻」、それに独立した三人の子どもたち、生田(川崎市北部)の町の人々が、まるで風景画のなかの点景のように描かれます。
庄野が亡くなったのは平成21年のことでしたが、その十年ほど前、脳出血で倒れ、それ以来、一日三度の散歩を欠かさず続けていました。はじめのころは「妻」が付き添い、それが杖になり、そして最後のころは、一人でゆっくりゆっくり歩いていました。その文章のように。「山田さんの鈴虫」は、そのころの作品です。
就寝前のハーモニカは、散歩と同様、大切な日課のひとつ。「私」の吹くハーモニカに合わせて「妻」が歌います。終わったとき、「『いい歌だな』『いい歌ですね』と二人でたたえる」。
安岡章太郎から届けられたポンカンを食べたときも、「『おいしいな』『おいしいね』と二人で感心しながら頂く」。
騒がしく揺れ動いている世間はここにはありません。ストーリーらしき起伏もなく、淡々と家族、町の人々、ご近所の山田さんからいただいた鈴虫や自然との交流を綴った文章が流れてゆきます。たちどころに消えて、次の瞬間にはこの世からなくなり二度と戻らない「今」をいとおしむかのように。
『生きていることは、やっぱり懐かしいことだな』という感動を与える小説を書きたい」──と、著者はかつてエッセイで書きました。 「入江さん(庄野の知人の画家)は決して人目を惹きつけようという絵はおかきにならない。ただ、ご自分の好みに合った風景だけをとり上げてかかれる。そこがいい」──は本書の中の一説ですが、はからずも著者の文学観がポロリと顔をのぞかせています。
余談ですが、私はそのころ、庄野邸のすぐ近く(50mも離れていませんでした)に住んでいて、散歩する姿をよく目にしていました。お近くだったということもあり、当時、私は庄野の作品をよく読んでいました。『プールサイド小景』のような初期の代表作はもちろん、生田の町に暮らす日々をゆったり描いた晩年の作品まで。自分の住む町の景色や見知った人々と作品の中で再会する妙な感覚を楽しんでいたのだと思います。
と同時に、私は庄野の文章から多くのことを学ぼうとしていました。そのころの読書ノートには、随筆集『自分の羽根』(講談社文芸文庫)から次の一節が描き抜かれていました。庄野が子供と羽根つきをしたことから得た「文学的感想」の一節から。
「私は自分の経験したことだけを書きたいと思う。徹底的にそうしたいと考える。但し、この経験は直接私がしたことだけを指すのではなくて、人から聞いたことでも、何かで読んだことでも、それが私の生活感情に強くふれ、自分にとって痛切に感じられることは、私の経験の中に含める。私は作品を書くのにそれ以外の何物にもよることを欲しない。つまり私は自分の前に飛んで来る羽根だけを打ち返したい。私の羽根でないものは、打たない。私にとって何でもないことは、他の人にとって大事であろうと、世間で重要視されることであろうと、私にはどうでもいいことである」
最近ではすっかり忘れてしまった、「書く」ことの基本に立ち返らせてくれる文章です。
馬場先智明